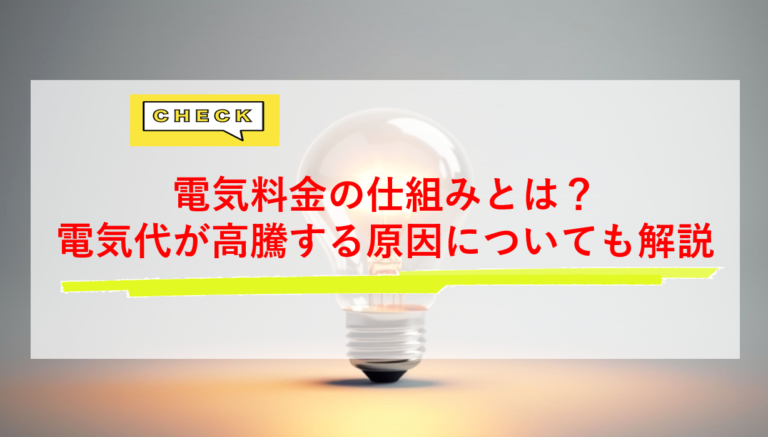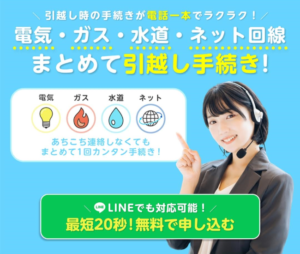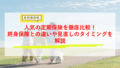月々の電気料金を節約したいのであればまず、電気料金の仕組みについて理解することが大事です。
電気料金の仕組みが分かれば高くなる原因についてもわかります。
そこで今回は電気料金の仕組みについて詳しくご紹介します。
電気料金の仕組みとは?
電気料金は以下の計算式によって求められます。
また電力量料金単価の決定については消費者が不当な金額を請求されないようにするため、以下の「原価主義の原則」「公正報酬の原則」「電気の使用者に対する公平の原則」の3原則に基づき設定されています。
- 原価主義の原則:発電などに必要な原価を適正に算出した上で、適正な利潤を加えた料金を定めること
- 公正報酬の原則:設備投資等の資金調達コストとして、事業の報酬は公正なものでなければならない。
- 電気の使用者に対する公平の原則:電気事業の公益性という特質上、消費者間の公平性を保てるよう料金を設定しなければならない
電気代を構成する要素は3つある
電気代は「基本料金」「電力量料金」「燃料費調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」より構成されています。
ここでは、それぞれの特徴について詳しくご紹介します。
基本料金
「基本料金」とは最低料金のことで、電力会社・プラン・アンペア数によって異なります。
電力使用量にかかわらず、毎月一定の金額が基本料金として請求されるため、月にまったく電気を使用しなかったとしても基本料金に関しては必ず支払わなければいけません。
平均的には家庭1軒あたりの平均アンペアである30A契約の基本料金もしくは40A契約の基本料金を設定しているところがほとんどで、なかには基本料金を0円としているところもあります。
なお電気料金の基本料金の主な内訳は、「発電の設備費」「人件費」「機材費」「その他諸経費」が挙げられます。
おもに電力会社が発電を行う上で必要な費用を基本料金でまかなっているということになりますね。
電力量料金
「電力料金」とは使用した電力量に応じて金額が変わる従量課金型の料金のことを指します。
電気を多く使うほど電力量料金が上がり、電気代の請求額も高くなる仕組みとなっています。
また電力量料金は以下の計算式で求められます。
ほとんどの電力会社で3段階料金制度が採用されており、電気の使用量が増えて段階が上がるほど、電力量料金単価も高くなります。
電気の使用量が多ければ多いほど割高になります。
燃料費調整額
燃料費調整額とは、発電にかかる燃料コストを電気料金に反映させたものです。
燃料価格が高騰すると電力会社の経営に大きなダメージを与えてしまうので、燃料価格の高騰から電力会社の経営を保護することを目的として導入されました。
燃料費調整額は電力量料金に組み込まれており、以下の計算式で求められます。
燃料価格が上昇すれば燃料費調整額が電気料金に加算され、燃料価格が低下したときには電気料金から差し引かれるようになっています。
つまり多くの人が燃料費を負担すればその分、電気代も安くなるということですね。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」とは、再生可能エネルギーで発電された電気を買い取るために課されている料金のことを指し、電力会社を通じて国の指定機関に支払われています。
太陽光や風力などの再エネで発電された電気は、再エネの電気を世の中に広く普及させるために、電力会社が買い取っています。
しかし買い取られた再エネの電気は一般にも供給されているため、消費者にも負担がかかっています。
ちなみに「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は以下の計算式で求められます。
単価は経済産業大臣が年度ごとに決定しており、全国一律です。
電気料金制の種類
電気料金制には大きく以下の3つの種類に分けられます。
ここでは、それぞれの電気料金制の特徴についてご紹介します。
定額料金制
「定額料金制」とは、使用電力量にかかわらず一定の料金を支払う制度のことを指します。
電力を多く使っても、まったく使わなくても同じ料金がかかるといった特徴があるので、普段からたくさんの電力を使う人におすすめです。
従量料金制
「従量料金制」は15kWhを最低使用量とし、15kWhを超えて使用した分は使用量に応じた料金がかかる仕組みです。
おもにほとんどの一般家庭で導入されているのがこの、従量料金制だといわれています。
基本料金制
「基本料金制」とは、基本料金+使用電力に応じた料金がかかるものとなっており、「二部料金制」と呼ばれることもあります。
おもに事業所や工場など、電力を多く使う場所に導入されています。
ケース別!電気料金の平均
電気料金はケースによって異なります。
そこでここでは総務省が発表した2022年のデータを元に、世帯人数別・地域別の電気料金の平均についてご紹介します。
世帯人数別の電気料金の平均
世帯人数別の電気料金の平均は以下の通りとなります。
| 単身 | 6,808円 |
|---|---|
| 2人 | 11,307円 |
| 3人 | 13,157円 |
| 4人 | 13,948円 |
当然ですが、世帯人数が増えるほど電力を消費するため電気料金も高くなっていきます。
地域別の電気料金の平均
地域別の電気料金の平均は以下の通りとなります。
| 北海道 | 13,084円 |
|---|---|
| 東北 | 13,835円 |
| 関東 | 12,262円 |
| 北陸 | 15,517円 |
| 東海 | 12,439円 |
| 近畿 | 12,221円 |
| 中国 | 14,743円 |
| 四国 | 13,450円 |
| 九州 | 11,894円 |
| 沖縄 | 11,616円 |
地域により電気料金の平均に差があるのは、地域を管轄する大手電力会社ごとの従量料金単価が異なるからだといわれています。
たとえば北陸や東北、北海道などの電気料金の平均が高くなっているのは、「世帯ごとの家屋が広い」「気温が低く、暖房器具を使う頻度や時間が長い」ことが挙げられます。
反対に関東や関西には大手の電力会社があり、たくさんの利用者が消費することから全国的に見るとやや低めになっています。
参考:総務省
電気料金が高騰する原因
電気料金が高騰するおもな原因としては以下のものが考えられます。
国内の電力供給が不足している
電気料金が高騰している原因としてまず、国内の電力供給不足が考えられます。
現在、東日本大震災後に原子力発電が相次いで停止し、供給量全体に大きな影響を及ぼしているといわれています。
また火力発電の老朽化による休廃止が進んでおり、国内の電力供給量の大部分を占める火力発電の供給量が減っていることも原因のひとつとして挙げられます。
以上のことから、需要に対して供給が追い付かなくなり、電気料金の上昇につながっているのです。
燃料費調整額が上昇している
国内の電源構成の大部分を占める火力発電は、天然ガス・石炭・石油などの化石燃料を使って発電しており、そのほとんどが輸入に頼っています。
したがって国際情勢や円安などさまざまな影響を受けると燃料費が上昇します。
火力発電のコストが大きくなり、燃料費調整額や電気料金も上がっていくようになります。
ただし燃料費調整額は近年上昇傾向にあるものの、2023年3月あたりから徐々に安定しているといわれています。
再生可能エネルギー発電促進賦課金の高騰
再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移は2012年から、単価は一度も下落することなく上昇し続けており、電気料金の高騰にも影響しています。
上昇の要因としては、おもに再生可能エネルギーの固定価格買取制度を使用した再生可能エネルギーの導入が進んでいることが挙げられます。
導入が進むことでそれだけ電力会社が買い取る再エネの量は増えるため、負担額も増大していく傾向にあります。
円安による燃料輸入費の上昇
円安によって燃料輸入費が挙がっていることも、電気料金の高騰に影響を与えていると考えられています。
円安になると輸入費が高くなるため、火力発電に必要な燃料コストが高くなるため、結果的に電気料金も上がるのです。
円安の水準は依然として高い状態が続いているので、これからも上昇していくと予想されています。
電気料金を節約する方法
最後に電気料金を節約する方法についていくつかご紹介します。
電気料金を節約したい方は以下の点を見直してみるといいでしょう。
契約アンペア
基本料金がアンペア制となっている場合、契約アンペア数を見直すことで節約できる可能性があります。
契約アンペア数は高いとその分基本料金が高く、下げれば基本料金が安くなります。
したがってこれまでブレーカーがほとんど落ちたことがないのであれば、契約アンペア数を見直すことをおすすめします。
たとえば契約アンペア数が40Aで不自由なく暮らせていたのであれば、30Aに下げてもそこまで不自由に感じないこともあります。
契約プラン
ほとんどの方は「従量電灯プラン」と呼ばれる、電力使用量に応じて電気料金が高くなる特徴のプランを設定しているといわれています。
したがって電気代を安く抑えたい場合は、契約プランの見直しも検討してみてください。
各電力会社からさまざまなプランが提供されているので、これまでずっと同じプランを利用している方こそ、一度見直してみるといいでしょう。
たとえば時間帯によって割引を受けられるプランやガスや通信とセットのプランがあり、自身の生活スタイルに合った最適なプランを選ぶことで大幅な節約につながる可能性があります。
現在利用中の電力会社のプランや利用状況をチェックし、より費用を安く抑えられるところはないか探してみて下さい。
電力会社自体を変更するのもひとつ
電力小売自由化されて以降、消費者は一昔前よりもさまざまな電力会社を選べるようになりました。
したがって電気料金を節約したいのなら、電力会社自体そのものを変更するのもひとつです。
電力会社の乗り換えを検討する際、電気料金プランだけでなくサービス内容も比較するのがポイントです。
なぜならよく確かめずに乗り換えると、自身のライフスタイルに合っていないとかえって高くつく恐れがあるためです。
電力会社を変更したからといって、電気の品質が低下することはないので、ぜひ検討してみてください。
電気料金の仕組みを理解すれば節電につながる!
今回は電気料金の仕組みについて詳しくご紹介してきました。
電気料金は様々な要素で構成されており、世界情勢による輸入費の上昇や地域の環境の影響などによっても変動します。
電気料金の仕組みを理解すれば、自身の電気代の節約にもつながるので知っておくといいでしょう。
また電気料金の節約を目指すのであれば、加入しているプランや電力会社について見直してみるのもおすすめです。