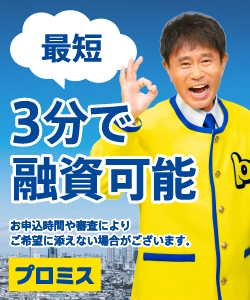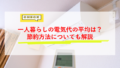今から20年・30年先、そして老後の自分はいったいどうなっているのか。
老後の2,000万円問題など、将来を心配する声をよく耳にします。
そのような中で「今のうちに将来のために貯蓄をし、早期に退職したい」などといった取り組みが注目されています。
「セミリタイア」とは、完全に仕事をやめてしまうわけではありません。
辞書などで定義づけされてはおりませんが、
「半分仕事をし、半分自分の時間に使える」
このようなことがいえるのではないでしょうか。
簡単にいうと、正社員から好きなアルバイトに変更できる状態といえます。
では、適度な経済的自由・精神的自由「セミリタイア」を目指されている方へ、知っていて損はない情報をお伝えしていきます。
これらの情報を分かりやすくシミュレーション形式でお伝えし、セミリタイアへの近道へとご案内いたします。
この記事を書いたライター
 けい@投資×節約
けい@投資×節約
1991年生まれ。家族との時間を増やす為、節約×資産運用でセミリタイアを目指しております。よろしくお願いします♪
1. まずは資産管理を行い、お金の流れを知ろう
会社に勤める生活をしていれば、収入と支出が発生します。
資産を管理していく為に収入と支出を把握し、お金の流れを把握しましょう。
その中で資産形成がとても重要なポイントになってきます。
収入の積み重ねを行う資産形成で、大切なポイントが2つあります。
- ポイント1:収入を増やすこと。
- ポイント2:支出を減らすこと。
まずは、ポイント1をどうしていけばいいのか。
これは勤め先の昇格、転職や副業などありますが余剰資産があれば、その資産を運用することで収入を増やす方法もありますので、目次3「国の制度を最大限に活用しよう」にて詳しく説明していきます。
次に、ポイント2をどうしていけばいいのか。
支出を減らすためには、固定費の見直しを行いましょう。
固定費の削減の例では
- 携帯料金の見直し
- 保険の見直し
- 電気代の見直し
などが挙げられます。
携帯料金の見直し(携帯を大手キャリアから格安SIMに変更)
たとえば大手キャリア「12,000円」を支払っているとすると格安SIMにすると平均「3,000円」程(プランによって異なります)毎月9,000円の固定費削減でき、10年で1,080,000円、30年で3,240,000円の削減ができます。
家族4人なら、大手キャリアから格安SIMに変更するだけで3人分タダになってしますね。
もちろん、格安SIMにすると通信速度が遅くなったりなどのデメリットもありますので、契約する前にしっかり内容を確認していきましょう。
保険の見直し(保険の過剰加入に注意)
保険の営業マンは「万が一の時に備えて」と商品を勧めてきます。
もちろん、万が一何かあれば保険に加入していると備えられます。
しかし安心には盲点があり、それは保険の過剰加入です。
ライフプランに合わせた保険の加入をお勧めされますが、本当に保険料金の支払いで家計を圧迫していないか必ず確認しましょう。
保険を検討するときは自分が必要な最低限の備えを意識した上で店頭の方と相談することをお勧めします。
電気代の見直し(おすすめプランを確認)
電気代の見直で、まず意識したいところは各電力会社が提供しているプランです。
会社により異なりますが、電気を使用する時間帯に合わせて電気料金を安くできるプランや、頻繁に使用する電気代のかかりやすいコンセントを対象に節電するプランなどがあります。
プランの変更により、毎月2,000円程安くなる実例もあげられています。
生涯電力は生活で必須になってきますので10年続けば240,000円、30年続けば、720,000円の節約につながります。
もし、あなたの加入されている電力会社のプランがいくつかあるなら一度プランの見直しをされてみてはいかがでしょうか。
2. セミリタイアへの近道は、節約
 セミリタイアを目指している方へ
セミリタイアを目指している方へ
今すぐ収入を増やしてセミリタイアへの近道をすることは難しいですが、今すぐに行動を変えれば支出を下げることは可能です。
10,000円の収入をあげるのと10,000円の支出を下げることは、残る資産とはしては同じですよね!
では今から厳選する節約術3つを紹介していきます。
節約術その1(生活スタイルに着目)
まず確認していただきたいのは、生活スタイルです。
たとえば、出勤時・学校の登校時・休日休暇などに水筒は持参されていますか?
とても小さなことだと思いますが一度、自動販売機や飲食店で購入されてる金額と比較していきます。
水筒にお茶やコーヒーを持参する金額を1人あたり30円とします。(およそ、お茶パック10円・コーヒードリップ20円)
一方、自動販売機や飲食店で購入する場合、平均して300円程。(およそ、自動販売機150円・飲食店450円)
その差は1人あたり1日270円です。
つまり、1人あたり1ヶ月8,100円の節約ができ、4人家族であれば1ヶ月32,400円の節約になります。
たとえば、4人家族の場合、10年・30年続けるとどうなるかみていきましょう。
- 10年で3,888,000円
- 30年で11,664,000円の節約となります。
1人あたりだと10年で972,000円、30年で2,916,000円なので家族一丸となり、節約をしていけば節約の力は増します。
節約術その2(衣食住の食について着目)
自炊をされている方や飲食店を通して食事をとっている方、いろいろな方がいらっしゃると思います。
その中で自炊をされている方に着目した節約術をお伝えします。
- 1週間に1度は冷蔵庫を空にする。
- 行きつけのスーパーを決めておく。
- 買い物のメモをとっておく。
この3つのポイントをクリアすることで食品ロスを防ぎ、節約しながら自炊を楽しむことができます。
では具体的にお伝えしていきます。
まず1週間に1度、冷蔵庫を空にすることを意識することにより自分たちがどれだけの食量を必要とするかが見えてきます。
多すぎた日、少なすぎた日、そのような日が多々あると思いますが、その時はメモをとっておきましょう。
適量な食事をとり1週間に1度冷蔵庫を空にすることで食品ロスを防ぎ、ムダな出費を防ぐことができます。
「セール中だから念のために買っておく」はやめておきましょう。
また行きつけのスーパーを決めておけば、「ポイント付与や現金還元」がつきます。
決められた日にポイント〇倍日や株主優待制度(イオン)などで、賢くポイントをためて節約していきましょう。
ではそれらのことがどれだけのムダの出費を防ぎ、節約ができるかみていきましょう。
捨ててしまいがちな食品ランキングとして挙げられているのは、「野菜や納豆・豆腐など」です。
たとえば、野菜270円、納豆1パック30円、豆腐100円、これらを1週間に1度捨ててしまうと400円のムダになります。
400円のムダの出費を防げば10年で192,000円、30年で576,000円となります。
また、毎月の食事の出費が30,000円と仮定しポイント付与+現金還元率を5%とすると、1ヶ月1,500円分のポイント付与または現金還元されます。
10年続ければ180,000円、30年続ければ540,000円となります。

節約術3(楽天市場のポイントに着目)
現在ネット通販の人気が急上昇しております。
そのような中でポイント還元が豊富な楽天市場に注目していきます。
楽天市場にはSPU(スーパーポイントアッププログラム)という制度があり、さまざまなシステムと連動させることにより固定のポイントが上がる仕組みとなっております。
たとえば楽天会員になり、楽天カード(無料)をつくり、楽天銀行と連動させ、楽天アプリで楽天市場を利用すると、固定ポイントが4.5倍増えます。(その他にさまざまなポイントアップがあります)
すべて無料なのではじめに設定さえしてしまえばSPU制度は攻略できます。
さらに楽天市場にはポイントアップのイベントが月に1~2回開催され、そのイベントに固定ポイントが上乗せされることが多いです。
イベント+固定ポイントを活用し日用品を購入したとき、どれだけの節約になるかみていきましょう。
日用品が1ヶ月に20,000円で、15倍ポイントがつく場合、
- 1ヶ月に3,000円の節約になります。
- 10年で360,000円、30年で1,080,000円となります。
楽天市場には日用品以外にも多彩なジャンルの商品を扱っていますので他のネットショッピング会社と値段比較しながら安いものを買っていきましょう。(ポイントがたくさんつくから楽天市場に決定、ではなくポイント付与を差し引いた金額での比較を推奨します。)
また、楽天ポイントは期間限定ポイントもありますので、楽天市場でポイントを使用しタダでお買い物をしたり、楽天モバイル・楽天でんきなどにもポイント使用が可能です。
お近くのマクドナルドなど、身近に楽天ポイントを使用できるところで、早めに消費していきましょう。

3. 国の制度を最大限に活用しよう
節約を実施し「0から生まれたお金」を貯蓄する中で、国の制度「NISA」を利用することで貯蓄するお金を運用していきましょう。
NISAとは:株式や投資信託の売却益や配当への税率(20.315%)を期間限定(2種類がありNISA(5年)、積立NISA(20年)で非課税とする制度。
節約で生まれた資産を教育費や、老後のお金に預金通帳へおいておくのがスタンダートかと思いますが、
そのお金を預金通帳に眠らせておくと年利0.3%程、お金に働いてもらい(投資信託など)国の制度(NISA)を利用することで年利を3~5%の資産を増やすことができるかもしれません。
つまりNISAは、お金の運用にかかる税率(20.315%)を非課税にする役割があります。
(※非課税は売却益・配当に限る)
それでは今まで紹介させていただいた節約(0から生まれたお金)をまとめ、「預金通帳 年利0.3%」と「投資信託 年利4%」の違いをみていきましょう。
はじめに、節約のまとめについて
- 携帯代金:10年で 1,080,000円、30年で 3,240,000円 (1ヶ月9,000円)
- 電気代金:10年で 240,000円、30年で 720,000円 (1ヶ月2,000円)
- 水筒持参:10年で 972,000円、30年で 2,916,000円 (1ヶ月8,100円)
- 食見直し:10年で 180,000円、30年で 540,000円 (1ヶ月1,500円)
- 楽天市場:10年で 360,000円、30年で 1,080,000円 (1ヶ月3,000円)
これらを足し算すると、1ヶ月あたり 23,600円 となります。
つまり、5つの節約を意識し実施するだけで23,600円ものお金が生まれたのです。
次に「違い」についてみていきましょう。
1ヶ月あたり23,600円を「預金通帳(0.3%)で運用した場合」
10年で2,874,543円、30年で8,888,891円となり1ヶ月あたり23,600円を「投資信託(4%)で運用した場合(NISA利用)」10年で3,475,095円、30年で16,379,566円となります。
- 10年の運用で投資信託は預金通帳に対して+ 600,552円
- 30年の運用で投資信託は預金通帳に対して+7,490,675円
という結果がでました。
NISAに関しては期間限定なので30年の運用はできず途中課税対象となりますが、およそ7,000,000円の利益を見込めます。(投資はリスクがあり、自己責任になります。)
NISAの厳選する投資信託の商品は160本以上あり、その中でも全世界に分散投資ができるものがあります。
1つの企業に集中的に投資をするより、全世界へのリスク分散は安心できますね。
証券窓口などで契約されるのであれば、特に管理費用に注意してください。
投資信託は大切な資産を積み立ていきますので、管理費用が高ければなかなか貯まっていきません。
商品の管理費用・純資産など必要な情報を理解していくことが必要です。
大切な資産を運用するので、できれば自ら投資信託の商品を選定することをお勧めします。
繰り返しになりますが国の制度であるNISAは税率(20.315%)を非課税にしてもらえる制度です。
資産を預金通帳に眠らせておくのではなく、資産に働いてもらう選択もあるのではないでしょうか。
セミリタイアを目指す上で大切なこと
ここまでで、セミリタイアへの近道になるツールをシミュレーション形式でいくつかご紹介させていただきました。
現在あなたが20歳だとしたら30年後になる50歳には節約のみでシミュレーションをした8桁の資産が手元にあるかもしれませんね。
ただ、セミリタイアを早くしたいという理由で焦ってはいけません。
最後に、セミリタイアを目指す上で大切なことお伝えしていきます。
生活防衛費を確保しておく
最低でも1年間の支出額は確保しておきましょう。
セミリタイアの近道の一つとして資産運用を紹介しましたが、結果に焦り貯蓄をすべて投資してしまうと株価の上下で精神的に不安定になってしまいます。
安定し、心に余裕を持ちながら運用する為には生活防衛費の確保は必須です。
収入と支出が比例しない
0から生まれたお金を、すぐに使用してしまうと節約した意味がありません。
人は資産が増えると、収入と支出が比例して価値観を変えてしまう傾向があります。
セミリタイアを目指されるのであれば価値観を変えないことが大切です。
セミリタイアという目標を計画的に行う
たとえば投資に5,000万円を年率4%を運用することで不労所得として毎年200万円のお金が手に入ります。
では5,000万円を貯めるためにはどのようにしていくか。
計画的に、家計ルールを定め、ぶれない軸と継続がセミリタイアという目標を達成する秘訣です。
セミリタイア後の目標を明確にしておく
セミリタイアを達成された方の意見として「想像以上に時間が余り、することがなくなった。」などの意見が挙げられております。
セミリタイア後の目標を明確化することで第2の人生ライフを充実させ、楽しめるのではないでしょうか。
また、目標の明確化により一番大切な「セミリタイアを目指す」という気持ちが強くなると思います。
現在の年間休日の平均が108.9日といわれています。
(厚生労働省が実施した「平成31年就労条件綜合調査」による情報)
年間労働256日の半分128日を自分の時間に使えること、これがセミリタイアです。
人生の労働時間の半分を掴み取るか、取らないかは今からの行動で決められるのではないでしょうか。(決して無理はせず、生活スタイルに合わせた行動を推奨します)
以上、「セミリタイアのためのお金のコラム」でした。